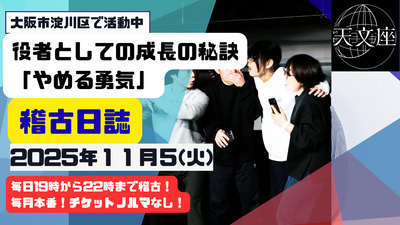
役者としての成長の秘訣:「やめる勇気」
熱量あふれる劇団の日常
劇団天文座は、2020年8月10日に旗揚げされ、5年以上にわたり活動を続けている劇団です。稽古は原則として毎日行われており、そのスタイルは徹底して実践的です。
稽古場では、プロの俳優を目指す真剣な取り組みだけでなく、ユーモラスなやり取りも頻繁に見られます。最近のブームにちなんだ「炭治郎選手権」が開催されたり、「恋の呼吸を使いたい!」という声が飛び交ったり、エスプレッソマシンのモノマネで場を和ませたりと、笑いの絶えない和気藹々とした雰囲気の中で稽古が進んでいきます。
柔軟な活動スタイルと確かな実績
私たちの活動スタイルは、驚くほど柔軟です。稽古への参加は強制ではなく、座長自ら「休んでください」と言うほど。好きな時間に参加できるシステムで、本番の日以外は希望を聞いてキャスティングされる形式です。月謝は1万円(ペリカでもOK)で、まさに「サブスク」のような感覚で利用できます。
この実践重視のスタイルが功を奏し、私たちの劇団の出身者からは、すでに4名が東京のプロ劇団で活躍しているという確かな実績があります。
また、公演回数の多さも私たちの特徴です。最も多かった年には年間142ステージをこなし、最近でも年間50ステージ程度を目標としています。稽古では、30分程度の作品をわずか2時間半で制作し、脚本、音響、照明などのパート分けまで行うというスパルタな指導も行っています。
演技の核心に迫る「やめる」哲学
私たちの稽古で最も大切にしているのが、座長が提唱する独自の演技指導法——「やめること」の重要性です。
一般的な演技指導では、「何か新しいことを足していこう」と考えがちです。しかし、私たちは真逆のアプローチを取ります。それが**「やめていく」**ことへの焦点です。
役者が「パワーを出したい」と考えたり、「大きな声を出す」ことに意識を向けるのは、結果を求める行為に他なりません。しかし、本当に大切なのは、その結果に至るまでのプロセスです。
座長は、役者に対し、「そのポーズをやめて」「その表情をやめて」と、今やっていることを辞めるように指示します。
なぜなら、「何かをしようと思ってやる動き」は遅く、ぎこちないのに対し、**「何かをやめた結果、次の動きが出るのが人間」**だからです。
「やめる勇気」が創造性を生む
たとえば、止まろうと思って止まることもありますが、基本的には「歩くのをやめる」から止まります。つまり、「止まる」は結果であり、「やめる」はプロセスなのです。
ベテランの役者ほど、技術や知識があるがゆえに、自分を「よく見せよう」としたり、「何かを表現しよう」という意識が先行しがちです。座長は、これを意図的にコントロールし、「いかにやめるか」を突き詰めることが、よりリアルで立体的な芝居を生む鍵だと語ります。
これは、単に楽をするという意味ではありません。「やめる」という行為は、実はとても怖いことです。なぜなら、次に何が起こるかわからないから。
しかし、この**「やめる勇気」**を持つことこそが、予測不能で魅力的な、真にクリエイティブな芝居へと繋がるのです。
社会貢献と未来の展望
私たち劇団天文座は、演劇活動を通じて社会への貢献も目指しています。
来年度からは株式会社化を目指し(インボイス制度対応の必要性もあるため)、さらには、全国を回り、発達障害を持つ子どもたちに演劇と出会う機会を提供する活動を本格的に稼働させる予定です。
座長は、以前、児童発達支援の分野で働いていた経験があり、劇場に来られない子どもたちにこそ演劇を届けたいという強い思いを持っています。
また、私たちはYouTubeでの発信も積極的で、ショートコントを毎日投稿しており、登録者数は1000人を超えています。
まとめ
劇団天文座の稽古は、単なる台本の読み合わせに留まらず、役者一人一人の人間性や深い演技哲学を探求する場です。
「役者として成長したいなら、何かを加えようとする前に、まずは今やっていることをやめてみる。」このシンプルな教えの中に、真に創造的な表現へのヒントが隠されているのではないでしょうか。
劇団天文座の今後の活躍と、新たな才能の覚醒にご期待ください!






