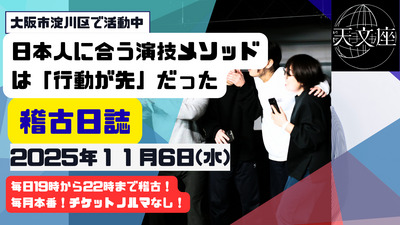
日本人に合う演技メソッドは「行動が先」だった
先日行われた劇団天文座の稽古から、演劇に対する深い洞察が得られました。今回は、現代演劇の土台となる演技システムの議論と、日本人の役者に最適なアプローチについて、稽古での具体的な指導内容とともにお届けします。
1. 舞台の土台:リアリズム演劇の起源
現代演劇の多くは、「リアリズム演劇」や「自然主義」と呼ばれるジャンルに基づいています。このシステムは、個人的な事情、個人的な感情、個人的な内面にフォーカスを当てた作品(イプセンやチェーホフなど)に対応するために、スタニスラフスキーによって考案されました。
それ以前は、劇団四季のような、ダンスや身体の使い方が巧みで、歌もうまく、声も美しい「職人芸」の芝居で成立していた時代がありました。しかし、個人的な悩みを大声で朗々と語るのは不自然であり、職人的な演技では個人の内面にフォーカスした作品を演じることができないという課題があったのです。
スタニスラフスキー・システム(感情が先)
スタニスラフスキー・システムの核となる考え方は、「楽しいから笑う」「悲しいから泣く」というものです。つまり、感情が行動を引き起こすというアプローチです。このやり方は、大正時代に日本に持ち帰られ、「新劇」として流行しました。
メイエルホリドの理論(行動が先)
一方で、スタニスラフスキーと意見を異にしたメイエルホリドは、「笑うから楽しい」「泣くから悲しい」という、行動や身体の動きが感情を生み出すという考え方にフォーカスしました。これは「動きの4原則」(オトカズ、ポサイル、トルモス、ストイカなど)としてまとめられています。
興味深いことに、スタニスラフスキー自身も晩年になって、メイエルホリドが唱えていた「動きが先だった」という考えが正しかったことに気づいたとされています。
2. 日本人に最適な演技メソッド:「行動が先」の文化背景
劇団天文座の稽古では、日本の風土において、スタニスラフスキー的な「感情が先」のアプローチは必ずしも適していないと指摘されました。
その理由は、日本の演劇芸能の歴史にあります。日本の伝統芸能(能、歌舞伎、落語など)は、動きがあって感情があるという文化で育まれてきました。私たち日本人の曽祖父や祖先も、この文化の中で育っています。
さらに、日本人は文化的に感情を表に出すことが苦手です。そのため、「感情を考えて動く」というアプローチを採ると、「合っているかな?」と否定的な思考(集合的無意識)に陥りやすく、クリエイティブな表現が難しくなってしまうのです。
久保栄先生もかつて、スタニスラフスキーのやり方はロシアでは適しているが、「日本人の風土には合っていない」と指摘し、日本人に合ったシステムを考えるべきだと述べていたそうです。
劇団天文座の指導者が10年間研究を重ねた結果、**「行動が先」のアプローチ、すなわち「笑うから楽しい」**という考え方こそが、日本人に合ったメソッドであるという結論に至っています。
3. 稽古の核:無意識の芝居から脱却する「オトカズ」と「やめること」
「行動が先」を実現するための具体的な指導として、特に「オトカズ」と「やめること(ビア・ネガティブ)」の重要性が繰り返し強調されました。
オトカズとは?
オトカズとは、次に自分がやる動きを思考すること、つまり準備のことです。例えば、立ち上がろうと思った上で立ち上がる、右足をどこに出そうか考えてから動く、といった、自分のやる動きを先に思考するプロセスです。
ビア・ネガティブ:「やめる」ことの力
そして、このオトカズで意識した行動をやめていくことが、「ビア・ネガティブ」です。
経験を積んだ役者は、セリフや行動を無意識(反射的)に出してしまいがちです。セリフの順番が来たから言っている、というような「無意識な芝居」が多くなります。
しかし、「やめる」という行為は、考えてから動くよりも簡単に行動に繋がるため、無意識の芝居を断ち切るために非常に有効です。
- セリフを言うこと:一番やめて欲しい行動は、セリフを言うことです。セリフが出るという結果に至るまでに、どれだけのオトカズの回数を踏み、どれだけ「やめる」ことができるかが重要になります。
- 具体的であること:やめる行動は具体的にすることが大事です。「近づきたい」というイメージをやめるのではなく、「3歩進もうと思った」という明確な行動をやめることが重要です。
4. 役者への具体的なフィードバックと指導
稽古では、参加者の経験に応じたアドバイスがありました。
新人役者への指導
演劇を始めたばかりの役者に対しては、まずは「型を作っていく段階」だと説明されました。日本の文化は、仕組み化や効率化が得意なため、まずは「お芝居とはこういうものか」という型を作った上で、それを将来的に破っていくのが最強の成長戦略であるとされています。
経験者役者への指導
経験を積んだ役者(型ができてしまっている役者)は、反射的な芝居から脱却するために、「オトカズの回数」を増やし、常に自分の行動を意識的に「やめていく」ことが求められます。自分のイメージや反射的な芝居から脱却するための、最も大変だが楽しいフェーズだと伝えられました。
声と姿勢の重要性
演技において最も重要な要素は、実は**聴覚(声)**であり、次に視覚(姿や動き)、そして演技そのものが3番目だと強調されました。
- 声の低い役者:声が低く太い人は、大きな声を出さなくても聞こえるため、ゆっくり話すことを意識するだけで、さらに良くなると指導されました。
- 姿勢:無意識のうちに片足重心になりがちなので、まっすぐ立つことを意識することで、本番での癖を防ぐことができると助言されています。
まとめ
劇団天文座の今回の稽古は、単なる台本の読み合わせに留まらず、演劇哲学の深い部分に触れる機会となりました。自分の行動を徹底的に意識し、「やめる」ことを通じて真のリアリティを追求するこのメソッドは、役者にとって大きな挑戦であり、成長の鍵となるでしょう。
例え話で理解を深める
オトカズとビア・ネガティブは、まるでカーナビをあえて無視する練習のようなものです。目的地(セリフや次の行動)は決まっているけれど、カーナビ(無意識や経験で培われた型)に言われるがまま動くのではなく、一度「この道を行こう(オトカズ)」と意識して、「でもやめてみる(ビア・ネガティブ)」を繰り返すことで、予測不可能な、よりリアルな行動が生まれるのです。






