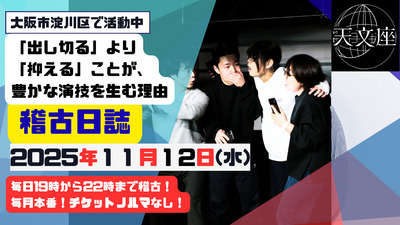
「出し切る」のではなく「抑える」ことが、豊かな演技を生む理由
900人の大ホールで求められる演技とは?
2025年11月12日の稽古は、これまでにない緊張感に包まれていました。
来たる公演の舞台は、900席を誇る大ホール。総収容人数1200人という規模に、稽古場には驚きと期待の声が響きます。サワモンが配役の喜びを口にする一方で、この大きな空間をどう「満たす」のか——その答えを探る、濃密な一日が始まりました。
この日の稽古で浮かび上がった、演技の「落とし穴」
「何も考えてやってない」という厳しい指摘
森本さんからのディレクションは、いつになく厳しいものでした。
「何も考えてやってない」
リクさんやカワムラさんに向けられたこの言葉は、演技における本質的な問題を突いています。反射的に動く、その場の感情だけで反応する——一見「自然」に見えるこの演技が、実は観客には「何もない」ように映ってしまうのです。
セリフや動きに至るまでの思考のプロセス。それがない芝居は、どれだけ身体が動いていても、観客からは「ゼロ」として認識される。この厳しい現実が、稽古場で共有されました。
「リッチな芝居」の正体——それは「制限」の中にある
100%出せる人が、あえて30%に抑える
この日、最も重要な哲学として共有されたのが、**「リッチな芝居」**の概念です。
「出せる人がすべて出してしまう芝居は、安っぽい」
感情を100%表現できる俳優が、あえて30%に抑える。声を張れる場面で、あえて静かに語る。この**「制限」こそが、演技に深みと豊かさをもたらす**のだと森本さんは語ります。
まるでスポーツのように、演技にも「ルール」と「制約」があります。その枠組みの中でどう輝くか——それを計算し尽くすことが、プロの俳優に求められる技術なのです。
俳優にとっての「負荷」とは何か
「すべてを反応でやってしまうのは、すでに俳優の体になっている証拠」
これは一見、褒め言葉のように聞こえます。しかし森本さんが伝えたかったのは、その先です。
俳優の体になっているからこそ、意識的に制限をかける思考が必要。自分にどれだけ「負荷」をかけられるか。それが、次のステージへの階段なのです。
空間が変われば、芝居も変わる
稽古場と本番会場の「サイズ感」の違い
もう一つの重要な学びは、空間への意識でした。
稽古場で「最適」だった芝居が、高槻やビッコロシアターの本番会場では機能しないことがあります。
- 大きな会場のサイズ感で小さな劇場でやると「うるさい」
- 小さな劇場の感覚で大ホールに立つと「届かない」
舞台俳優は、空間のサイズに合わせて演技を調整する能力が求められます。それは単なる声量の問題ではなく、エネルギーの配分、間の取り方、視線の届け方すべてに及ぶのです。
相手役への配慮——演技は「連携プレイ」
「自分の芝居が相手のセリフを食っていないか」
特に長尺のセリフシーンでは、話す側だけでなく聞く側の演技が重要になります。相手が気持ちよく演技できるように、自分の芝居をコントロールする。これもまた、「制限」の一つの形です。
各俳優への具体的アドバイス——成長のヒント
サワモンさんへ:声量と歌の課題
「声量を100%から150%(約45デシベル)に」
さらに興味深かったのが、歌の苦手意識の分析です。
「地声の筋肉が強く、裏声の筋肉が弱い体質」
この診断に基づき、裏声での練習を徹底することで歌唱力の向上が期待できるという、具体的なアプローチが示されました。
アカリさん、リクさんへ:間とリズムの調整
- リクさん:セリフの途中で「ビートを開けて落としていく」傾向
- アカリさん:不必要な「間」ができてしまう癖、動きとセリフが繋がりすぎる
これらは無意識の癖として現れますが、意識することで改善可能な技術的課題です。
アキラさんへ:「初めて」のコントラスト
カメラを扱うシーンでの指導が印象的でした。
「初めて触るかのように、恐る恐る、慎重に扱う」
この「初めての感覚」を演じることで、キャラクターに深みが生まれ、コントラストのある芝居になると指導されました。
また、基本的だが重要な原則も:
- 相手が話している時は、相手の顔を見る
- 自分が話す時は、観客に顔が見えるよう正面を向く
これは観客への配慮であり、プロとしての責任です。
「天井」からの脱却——さらなる成長への道
「現状、みんなの演技は天井に来ている」
森本さんからのこの厳しい言葉は、しかし絶望ではありません。むしろ、今からさらなる成長への道筋を明確にするための、熱いメッセージでした。
この日の稽古で繰り返し練習されたシーンたち——ポンティ公演の台本、理想郷「タオタラカ」への言及、オーディション詐欺の会話、初対面の距離感を描くシーン。これらすべてが、「制限」と「計算」という新しい視点で見直されることになります。
観客を喜ばせるために、俳優ができること
劇団のルールとして、週7日の稽古は推奨しないという「ワークライフバランス」の話題も出ました。これは単なる健康管理ではなく、**俳優が自ら考え、アイデアを出し合い、「共につくっていく」**ための余白を持つことの重要性を示しています。
舞台は、俳優だけのものではありません。
観に来てくださるお客様を喜ばせること。その一点のために、全員が計算され尽くした「リッチな芝居」を目指す。
まとめ:制約の中でこそ、最高のパフォーマンスが生まれる
この日の稽古が教えてくれたのは、演技はスポーツに似ているということです。
ルールや制約があるからこそ、その中でどう輝くかを考えることができる。制限があるからこそ、計算が生まれ、豊かさが生まれる。
「出し切る」のではなく「抑える」。
この一見矛盾したような原則が、実は演技の深みを生み出す鍵なのです。
900人の大ホールという新たな挑戦の場で、この学びがどう花開くのか。今から本番が楽しみでなりません。






