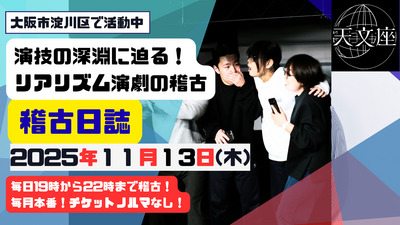
演技の深淵に迫る!リアリズム演劇の稽古
はじめに:演劇は「論理的思考のスポーツ」だった
「芝居って、感情を爆発させればいいんでしょ?」——もしあなたがそう思っているなら、この記事を読んだ後、その認識は180度変わるはずです。
2025年11月13日、とある劇団の稽古場。そこで繰り広げられていたのは、まるでチェスやサッカーの試合のように、一手一手が計算され、戦略が練られる、高度に論理的な演劇の世界でした。
今回の稽古で最も重視されたキーワード、それが**「選択肢(手札)」**です。
リアリズム演劇の基礎:「自然」を作るための徹底した技術
1. 声と身体の「癖」を徹底的に排除する
稽古場で最初に叩き込まれるのは、俳優の基本的な振る舞いです。しかし、その要求は想像以上に厳格でした。
演出からの指示:
- 理由がないのに大きな声を出さない
- 感情を「作る」声(作声)をゼロにする
- セリフを言う時は相手の顔を見る
- 前傾姿勢を直し、重心を崩さずまっすぐ立つ
- 体を揺らさない、無意識の癖を排除する
「普通に喋る」——たったそれだけのことが、舞台上では驚くほど難しい。日常生活では無意識に行っている行動も、観客の前では「演技臭さ」として露呈してしまうのです。
2. 「間」の魔法:動いて、止まって、それから話す
リアリズム演劇で最も重要視されるのが、セリフとセリフの間の**「間」**の扱い方です。
「人間は動いてから話すもの。でも芝居では、セリフを先に言ってから動いてしまう」この演出の言葉が、すべてを物語っています。
稽古で徹底されたルール:
この順序を守ることで、観客は俳優の「思考過程」を目撃することができます。セリフは「結果」であり、その結果が出てくるまでにどれだけ「過程」を積めるかが、芝居の質を決めるのです。
革新的概念:俳優の「選択肢(手札)」を広げる演劇論
芝居は「選択肢のゲーム」である
今回の稽古で繰り返し強調された核心的な概念——それが**「選択肢(手札)」**という考え方です。
「芝居とは、自分の行動やセリフによって、自分や相手の選択肢を増やすのか、減らすのかを考えるゲーム」この定義は、演劇に対する見方を根本から変える力を持っています。
選択肢を「潰す」NGパターン
❌ 相手に近づきすぎる セリフを言うために密着してしまうと、その後の自分の選択肢(さらに近づく、動くなど)がゼロになり、相手依存の演技になってしまいます。
稽古場での実例: ある俳優が、仲の良い友人同士のシーンで相手との距離を約1.5メートル空けるよう指示されました。理由は?「パーソナルスペースを保つことで、『近づく』という選択肢を残すため」です。
俳優に求められる「脳みそ」
俳優は集中力の7〜8割を演技に使い、残りの2割で常にこう自問し続ける必要があります。
「今ここで動いたら、全体の選択肢が増えるか、減るか?」
これは、まるでチェスプレイヤーが数手先を読むような、高度な思考プロセスです。
目から鱗!シーンの種類で戦略を変える「スポーツ理論」
二人芝居 = 野球
ピッチャー(喋る側)とバッター(聞く側)の関係
- ピッチャー:ストレートか変化球か(セリフの言い方やトーン)を選んでボールを投げる
- バッター:それに対してどう打ち返すか(セリフを返すタイミングやトーン)を判断する
シンプルですが、一対一の緊張感が研ぎ澄まされます。
三人以上のシーン = サッカー
全員が常に「走って」いなければならない
サッカーで最も難しいのは、ボールを持っていない選手も常に動き、ポジショニングを考え続けなければならない点です。演劇でも同じ。
セリフを言っていない俳優も、常に「自分の行動が全体の選択肢をどう変えるか」を考え続ける必要があります。
稽古場で飛び交ったリアルなフィードバック
ケース1:脚本分析の「構造」が弱い
ある俳優は「殺されないためにトラブルを解決する」という分析を持ってきましたが、演出から一蹴されました。
演出の指摘: 「それは機械的で、構造が弱い。シーンの目的、ユニット分け、ビート分けを明確にして。考えてくるのではなく、やってきてほしい」
ケース2:不安が強い俳優へ
「何をしていいか分からない」——そんな不安を抱える俳優には、まずセリフを覚えることが最優先とされました。
演出の言葉: 「受動的(言われたことだけやる)ではなく、能動的に動くこと。それが俳優の仕事です」
ケース3:動きながらカードを切り続ける俳優
ある俳優は「動きながらも選択肢を切り続けている」と高評価を受けました。しかし同時に、こんな指摘も。
「セリフが短いと、相手のリアクションの選択肢が出にくくなる。セリフの継続性も大事」
新人俳優の入団:緊張のない「パパ役」
今回、劇団に新たなメンバーが加わりました。人前で何かをすることに慣れており、緊張がない様子が確認されたといいます。
パパ役として、娘と話すシーンや同級生と話すシーンでは、相手との関係値を明確に変えることがディレクションの核心でした。
「喫煙所での会話」というシチュエーションが例に挙げられ、同じ人物でも場所や相手によって距離感や態度がどう変わるのか、その切り替えの精度が求められました。
演劇は「痛みと向き合う覚悟」を求める
稽古の合間、ある俳優がこう漏らしました。
「演劇って、自分の弱さや癖と向き合わされる。それが痛い」
しかし、その痛みこそが成長の証です。リアリズム演劇は、俳優に徹底的な自己観察と、論理的思考、そして身体的コントロールを要求します。
それはまるで、アスリートがトレーニングで自分の限界と向き合うのと同じ。演劇もまた、高度な競技なのです。
まとめ:演劇は「感情の爆発」ではなく「選択肢の芸術」
今回の稽古レポートを通じて見えてきたのは、リアリズム演劇の本質です。
演劇とは:
- すべての動作に「意図」と「選択肢」が存在する
- 俳優は常に「全体の選択肢を増やすか減らすか」を判断し続ける
- 感情を作るのではなく、過程を積み重ねることで自然に生まれる
- シーンの種類によって戦略を変える、論理的思考のスポーツ
まるでチェス、野球、サッカーのように、一つ一つのセリフや動きが「ボール」や「カード」として扱われ、戦略が練られていく——その様子は、演劇が単なる表現活動ではなく、論理と感性が融合した高度な芸術であることを物語っています。
次に舞台を観る時、俳優たちの「間」や「距離感」に注目してみてください。そこには、観客には見えない無数の「選択肢」が隠されているはずです。






