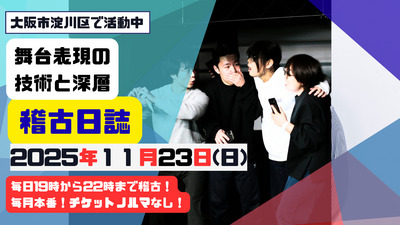
舞台表現の技術と深層
今回の集中稽古では、即興演技から特定シーンの精密な作り込みまで、幅広い訓練が行われました。指導者からの厳しくも的確なフィードバックを通じて、出演者たちは舞台表現の本質に迫る濃密な時間を過ごしました。
即興課題で探求した多彩なテーマ
稽古では、短時間で設定と役割を切り替えながら、さまざまなシーンでの即興劇に挑戦しました。
取り組んだテーマ例
- 戦国時代
- 商店街の八百屋
- ゆるキャラ全国大会
- 旅館の女将とバイト
- 結婚相談所に来た二人
- ジムでのトレーニング
- 絵本の世界
- 公園で筋トレする老人とそれを見る老婆
- 歯医者
- UFOに遭遇した人々
特に重要視されたのは「ネタの鮮度」です。ありきたりな喧嘩や予想できる展開は避け、観客が想像もしない展開を生み出すことが求められました。旅館のシーンでは、皿を洗う動作から寿司を作るという意外な展開や、配役を変えることでさらに面白さが増す可能性が示唆されました。
舞台技術と表現の核心
リズムと音のコントロール
演技における「音」と「リズム」の重要性が繰り返し強調されました。
- セリフのリズムが「ドン・タッタ・ドン」のように一定で、常に頭にアクセントがつく状態は避けるべきとされました
- どんなに内面を変えても、音やリズムが変わらなければ観客には違いが伝わらないという指摘
- セリフを「切る」タイミングを変えることで、音やリズムが変化し、演技の質が変わる
- 母音の形で声が広がる(拡散する)傾向を意識し、音の位置を正確に定めることの重要性
身体表現と目線の使い方
特定のシーンでは、従来とは異なるアプローチが提案されました。
- 身体のリズムを使わず、まっすぐに立ち、首や目線も変えずに演じる「サイレント」なプラン
- これは「早さ」ではなく「不気味さ」を強調するための演出方法
- 演技中に相手の顔を見続けるのは「普通の人間の行動」になってしまうため、避けるべきと指導されました
演技の「質」を変える
セリフの出し方や音の出し方が「普通の登場人物」になってしまうと、名前のない役と同じ質になってしまいます。そのため、意識的に「質を変える」ことが重要だと強調されました。
アンサンブルでの集団表現
集団シーンでは、個々の演技力だけでなく、全体としての完成度が追求されました。
間(ま)の詰め方
出演者がセリフを言う間隔が空きすぎている点が問題視されました。アンサンブルシーンでは、言いたいことを全員が言うだけでは不十分で、むしろ「詰める方が技術がいる」と説明されました。
リズムとグルーヴの共有
一部の出演者の演技や身体のリズムが死んでいる(グルーヴが死んでいる)ため、全体の調和が取れないという指摘がありました。また、一部の出演者が動けない状態になった場合、他の出演者がそれを受けて演技のプランを調整する必要性も示されました。
仮面を使った特殊な表現方法
今回の舞台では、登場人物の一部が無表情の仮面(マスク)を着用する予定であることが明かされました。
仮面使用の意図と訓練
- 仮面をかぶると匿名性が上がり、演技の制御が効かなくなるリスクがある
- そのため、着用前に細心の注意を払って身体と技術の制御をかける訓練が必要
- フランスの演劇に見られる「仮面のエチュード」と同様の概念
- 仮面が勝手に喋ってくれるようになる前に、基礎的な制御を徹底させる
俳優の心構えと演出の哲学
個人的な感情の排除
「舞台上では個人的な感情はいらない」という哲学が繰り返し強調されました。観客は出演者の「できた」「できなかった」という個人的な悔しさや喜びには関係なく、作品の質に対して対価を払っています。
「私はできます」「私は考えています」という態度(奢り高ぶる芝居)は、実際には何もできていないのと一緒であると厳しく指摘されました。
技術の限界を突破する
演技に「天井(限界値)」を設けている状態では成長が止まります。「現状できねえわけじゃなくて、集中してないだけ」という指摘は、出演者に対する強いメッセージでした。
指導者は、「できないことが嫌」だと思っている状態ではなく、むしろ「できないことを楽しむ」べきだと諭しました。
「火力マックス」な指導の意図
指導者は、出演者の悪い癖や自己満足的な芝居を破壊するために、あえて強い言葉やフィードバック(「ロードローラー」や「ハンマー」に喩えられる)を用いる「火力マックス」な指導を行っています。これは、出演者が現状に満足せず、より高い作品の質を目指すための手段であると説明されました。
今回の稽古は、技術的な精度とプロフェッショナルな俳優としての心構えの両面から、出演者の能力を最大限に引き出すことを目指した、非常に密度の濃い時間となりました。舞台作品の質を高めるために、一人ひとりが自分の限界を超えて挑戦し続ける姿勢が求められています。






